更新日:2024年10月29日 | Masaru
POSレジは、お店の会計作業を速く、簡単にしてくれる便利な道具です。日本では、このシステムがどれだけ使われているか、市場はどのくらい大きいのか、そして成長しているのかを見てみましょう。
さらに、どの会社のPOSレジが多くのお店で使われているかも紹介します。この情報を知ることで、事業者は自分のお店に最適な選択ができるようになります。

日本では、特にターミナルPOSレジの市場が大きく、モバイルPOSレジの市場も急速に成長しています。ターミナルPOSレジの市場規模は、2022年には約481億円に達し、成長率は22.3%でした。一方、モバイルPOSレジは、その便利さから多くの小規模事業者に選ばれており、2015年から2020年にかけて店舗数が350,000店に増えました。
国内でのシェアは、東芝テックが最も多く、信頼できる技術とサービスで多くの業界から支持されています。これらの情報をもとに、POSレジの導入を検討する場合は、その利点とともに、導入に伴う初期費用や使いこなすまでの時間も考えることが大切です。
このシステムがあれば、事業者は会計業務に追われることなく、もっと他の重要な仕事に集中できるようになります。その結果、全体の仕事の質が上がり、店舗の売り上げ向上にもつながるでしょう。
POSレジの市場規模と成長率

POSレジは、事業の効率化を実現する重要なツールです。本記事では、日本および世界におけるPOSレジの市場規模と成長率を詳しく解説します。最新の市場動向を把握し、あなたのビジネスにどのように活用できるかを考えましょう。
国内のターミナルPOSレジ市場規模と成長率
日本のターミナルPOSレジ市場は、近年さまざまな変動を経験しています。具体的には以下のような数字になっています。
- 2021年時点での市場規模は約400億円で、これは前年に比べて減少しています。
- 同年の出荷台数は約93,000台となり、市場の活動状況を示しています。
- 2017年にはコンビニエンスストアでの機器の置き換えが起こり、市場に大きな影響を与えました。
- 経済の不透明感や他の技術、特にタブレットPOSレジへの移行が影響を与え、市場は低迷しました。
- 2022年には市場が回復し、成長率22.3%を記録し、市場規模は約481億円に達する見込みです。
この情報から、日本のターミナルPOSレジ市場は変化に富んでおり、新しい技術の登場と経済状況の変化に敏感であることがわかります。
国内のモバイルPOSレジ市場規模
国内のモバイルPOSレジ市場は、過去5年間で著しい成長を遂げています。
具体的に見ていきましょう。
- 2015年から2020年までの導入店舗数は、99,000店から350,000店に急増しました。これは、小規模店や個人経営店を含むさまざまな業種での需要の高まりを反映しています。
- 同期間の市場規模も、23億円から140億円に大幅に拡大しています。これは、モバイルPOSレジが従来のターミナルPOSレジと比較して低コストで高機能であることから、多くの事業者が採用していることを示しています。
- モバイルPOSレジの普及が進む理由は、導入費用が10万円~20万円、月額利用料金が0円~2万円という低価格でありながら、高い機能性を備えていることにあります。
- さらに、スマートフォンやタブレットなど、日常的に利用している端末にPOSレジアプリをインストールするだけで利用できる製品が増えており、導入の手軽さもモバイルPOSレジの普及に貢献しています。
これだけ多くの店舗がPOSレジを導入している背景から、業務効率化は確実に行えることがわかります。
世界のターミナルPOSレジ市場規模と成長率
世界のターミナルPOSレジ市場も、活発な成長を遂げています。どのような成長が見られるでしょうか?
- 2020年の市場規模は722.8億ドルでした。この数字は、世界中のPOSターミナルの需要を反映しています。
- 2021年から2026年までの年平均成長率(CAGR)は8.3%と予測されており、2026年には市場規模が1162.7億ドルに達すると見込まれています。
- 最近のPOSレジは、会計ソフトや在庫管理システムなど、周辺機器や外部サービスとの連携が可能です。これにより、売上や在庫の管理が迅速かつ正確に行えるようになっています。
新型コロナウイルスの影響で、消費者は非接触決済を好む傾向にあります。POSレジは、キャッシュレス決済端末との連携や、セミセルフレジとして運用可能です。そのため、感染予防対策としてPOSレジを導入する店舗も増えています。
世界のクラウドPOSレジ市場規模と成長率
クラウドPOSレジは、その柔軟性とコスト効率の良さから、多くの企業に採用されています。このセグメントの市場は、技術の進化に伴い、今後も大きな成長が期待されます。実際、最新のデータによると、クラウドベースのソリューションへの投資が増加しており、それが市場成長を支えています。
世界のクラウドPOSレジ市場も急速に拡大しています。以下はその詳細です。
- 2020年の市場規模は22億ドルで、その後の成長が期待されています。
- 2021年以降の年平均成長率(CAGR)は24%と予測され、2027年には市場規模が100億ドルに達する見込みです。
- クラウドPOSレジは、柔軟性や拡張性が高く、多くの企業が採用しています。
日本市場では、2017年にピークを迎えました。その後、出荷金額は減少傾向にありますが、2019年でも609億円に達しています。大手コンビニチェーンの需要が増加したことが、2017年の出荷金額の増加に貢献しています。
クラウドPOSレジは今後多くの事業者が導入していくだろうと予想されている分野の一つです。
POSレジの普及率とシェア

POSレジシステムは、事業の運営をスムーズにし、顧客サービスを向上させるための重要なツールです。このセクションでは、日本国内および世界の市場におけるPOSレジの普及率とシェアについて詳しく掘り下げます。最新のデータを基に、どのメーカーが市場をリードしているのかを明らかにし、あなたの事業にとって最適な選択肢を見つける手助けをします。
日本におけるセルフレジの普及率
セルフレジは、お店での会計を早く、簡単にするシステムです。2021年の調査によると、スーパーマーケットではフルセルフレジが23.5%、セミセルフレジが72.2%の普及率を示しています。小さな店でも多く使われ始めており、これからもっと広がると見られます。
- 飲食店やクリニックでも導入が増えている。
- スーパーマーケットではセミセルフレジが大半を占める。
- 小規模店舗でも導入が進んでいる。
最低時給が上がっている背景から、人件費削減がテーマとなっていく企業が増加しており、セルフレジは人件費削減の観点からも非常に有効な手段の一つです。
国内ターミナルPOSレジメーカーのシェアランキング
POSレジは店舗での会計作業を早くこなすための大切な道具です。2018年の日本国内のシェアでは、東芝テックが一番多く、次にNEC、富士通フロンテックと続きます。これらのメーカーは技術も高く、信頼されています。
- シャープが約9%のシェアを持つ。
- その他のメーカーも含め、さまざまな選択肢がある。
- 寺岡精工は約6%のシェア。
POSレジを活用することで、日々の業務を効率よく進め、他の重要な仕事に集中できるようになります。
安定性を求める背景から大企業の端末を使用する動きがあります。
国内タブレットPOSレジのシェアランキング
タブレットPOSレジは操作が簡単でデザインも魅力的、多くの店舗で導入が進んでいます。特に、Airレジは709,000アカウントでトップ、スマレジが38,000店舗以上、ユビレジは30,000店舗以上で使用されており、それぞれが店舗の効率化に貢献しています。これらのシステムを導入することで、日々の会計業務が格段にスムーズになり、時間を節約できるようになります。
- Airレジは709,000アカウントで最も多くの店舗が利用。
- スマレジは38,000店舗以上で活用されており、広範囲にわたる導入が見られます。
- ユビレジも30,000店舗以上で導入され、堅実なシェアを維持。
タブレット型のPOSレジは使用する世代が若い世代が多いため、取り扱いが簡単であるために人気のサービスになっています。
世界のPOSレジのシェアランキング
世界のPOSレジ市場では、様々な国の企業が競争しています。2021年のデータによると、フランスのワールドラインがトップで3.8%のシェアを持ち、日本の東芝テックが2.7%で2位に位置しています。
その他、アメリカのベリフォンや中国のパックス・テクノロジーなどが続いています。これらの会社は、POS端末の技術やデザインで世界中の多くの店舗に支持されています。
- ワールドラインは3.8%で最も多くのシェアを持つフランスの会社。
- 東芝テックは2.7%のシェアで、世界で2番目に多くの店舗が利用。
- ベリフォンは2.1%のシェアでアメリカから。
- パックス・テクノロジーは1.1%で中国の会社。
日本企業がトップテン入りしているのは誇らしいことですね。POSレジは今後の発展が気になる企業が多く取り組んでいる事業の一つです。
【Amazon.co.jp限定】 バッファロー WiFi ルーター 無線 LAN Wi-Fi 7 11be トライバンド 6ストリーム 5764 + 2882 + 688 Mbps 有線 10Gbps エコパッケージ 【 iPhone 17 / 16e / 16 / 15 / Nintendo Switch / PS5 動作確認済み 】 WXR9300BE6P/N
【Amazon.co.jp限定】 TP-Link WiFi 無線LAN 中継機 Wi-Fi 5 11ac AC1200 866+300Mbps Wi-Fi中継機 コンパクト コンセント直指し【 iPhone16, ipad, Nintendo Switch 】OneMesh MU-MIMO アクセスポイント 有線LANポート かんたん設定 メーカー保証3年 RE330
15% オフインスタントWi-Fi TD11 105GB 1年間 自然故障保証付き バッテリーレス データ通信回線付き ポケットWiFi モバイル ワイファイ ルーター USB通信対応 契約・月額なし 買い切り 返却不要 プリペイド型 海外対応 (100GB+追加5GB付き)
まとめ:POSレジの普及率と市場規模、成長率は?国内シェアが多いのは?
POSレジシステムの導入は、事業の運営をスムーズにし、効率を大幅に向上させる手段です。日本国内では、ターミナルPOSレジの市場が成長を続けており、特にモバイルPOSレジやクラウドPOSレジの普及が著しいです。これらのシステムを活用することで、事業者は会計業務の時間を短縮し、人件費の削減が可能になります。
日本のターミナルPOSレジ市場は、2022年において市場規模が約481億円に達し、成長率は22.3%を記録しました。一方で、モバイルPOSレジは、その手軽さから特に小規模事業者に支持され、2015年から2020年にかけて店舗数が99,000店から350,000店へと急増しました。市場規模も23億円から140億円へと拡大しています。
世界市場でも、POSレジの需要は高まっており、特にクラウドベースのPOSレジ市場が注目されています。この市場は、2020年には22億ドルの規模であり、2027年までには100億ドルに達すると予測されています。
日本国内のターミナルPOSレジメーカーでは、東芝テックが最も多くのシェアを占めています。これに続いてNECや富士通フロンテックが位置しており、これらの企業は革新的な技術と信頼性の高いサービスで市場をリードしています。
このように、POSレジの市場は成長を続けており、その利用は事業の効率化に大きく寄与しています。事業者はこのツールを導入することで、会計業務の時間を減らし、その他の業務に集中することが可能になるため、全体の業務効率の向上が見込まれます。


当サイトでは、POSレジの導入による会計業務の効率化とその影響について、中立的な立場から情報を提供しています。目的は、POSシステムがどのように時間を節約し、コストを削減し、最終的には売上を向上させるかを、具体的なデータと共に解説することです。事業者が適切なPOSシステムを選び、業務をスムーズにし、より良い顧客サービスを提供できるよう支援します。当サイトでは、POSシステムのメリットとデメリットを公平に評価し、事業者が情報に基づいた決定を下せるように助けています。












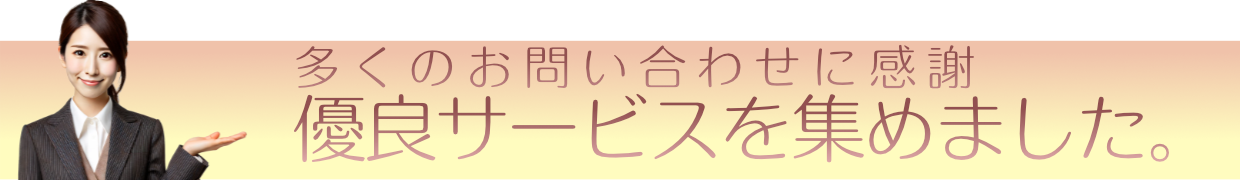






![[特徴] かんたんにつかえる、867 + 300Mbps の広範囲Wi-Fi中継機 [Wi-Fi範囲が広がる] WiFiルーター といっしょに使ってかんたんに範囲を拡張できます [アクセスポイント] 有線LANルーターとイーサネットで繋げれば、有線LANの親機をかんたん無線LAN化 [メッシュWiFi 対応] 同じくOneMesh対応のTP-Link製ルーターと繋げると簡単にメッシュWi-Fi環境を構築します [スマホでパパっと繋がる] スマホアプリTetherでかんたんにつながる](https://m.media-amazon.com/images/I/31p1BG1BuwL._SL160_.jpg)










